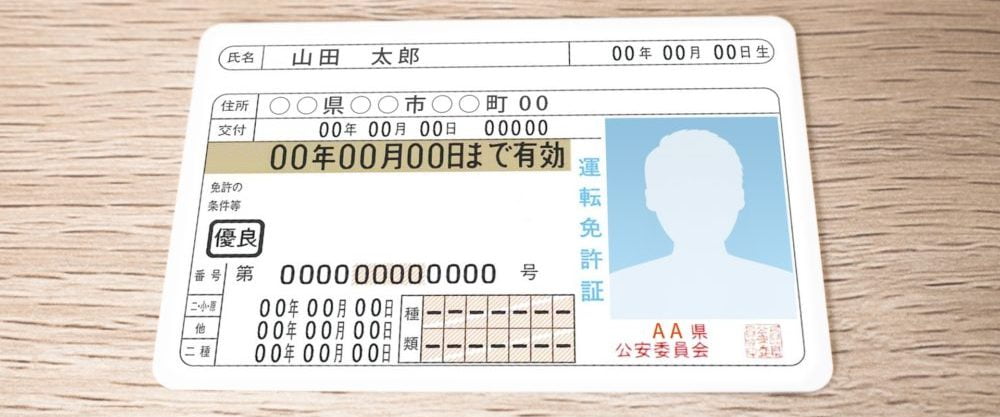原付のように速度や二段階右折の制限がない原付二種はとても人気があり、取得しようと考えている人は多いと思います。
しかし、原付とは違い自動車教習所に通って取得するのが一般的で通う手間がかかるのですが、
教習所に通わずに免許を所得できる一発試験も行われています。
今回はその一発試験の難易度や手順はどのようなものかを紹介します。
スポンサーリンク
原付二種125ccの免許の一発試験の難易度は?

原付二種に限った話ではないですが、一発試験の難易度はかなり高めです。
原付二種免許の正式名称は小型限定二輪免許と言います。
年によって異なりますが、小型限定二輪免許の合格率は5~10%程度が多く、高い年でも20%未満です。
平均受験回数も大体10~20回になっています。
小型限定二輪免許のAT限定の合格率は10~30%程度になっています。
平均受験回数もMTより少なく、3~7回程度です。
スポンサーリンク
原付二種125ccの免許の一発試験の受験手順は?

一発試験では、すべての試験が受験日当日に行われます。
事前の予約などは基本不要で、当日窓口で手続きを行います。
一部事前予約が必要な地域がありますので、事前に運転免許試験場に確認することをおすすめします。
試験日や時間等は、運転免許試験場によって異なるため確認しましょう。
持ち物
必要なものは、
- 免許証(持っている場合)
- 証明写真(証明写真は試験場でも撮影可能)
- お金
- ヘルメット(貸出がない場合)
- グローブ(貸出がない場合)
が必要です。
一発試験にかかる費用は、
| 試験手数料 | 2,600円 |
| 試験車使用料 | 1,450円 |
| 合計 | 4,050円 |
| 免許交付手数料 | 2,050円 |
| 取得時講習 | 12,000円 |
| 応急救護講習 | 4,200円 |
| 合計 | 22,300円 |
になりますので、お金が足りないことにならないように注意しましょう。
ヘルメットとグローブは貸し出ししているところが多いと思いますが、
貸し出ししていない場合もありますので、その場合は必要になります。
スポンサーリンク
試験の流れ
試験の流れとしては、
- 適性検査
- 学科試験
- 技能試験
の順番で行われます。
適性検査
適性検査は道路を安全に運転することができるかの身体検査です。
適性検査をクリアしなければ、学科試験へ進むことができず、免許を取得することができません。
内容は
- 視力検査(両目で0.7以上)(メガネ、コンタクト可)
- 色彩識別検査
- 運動能力検査
- 聴力検査(補聴器可)
です。
学科試験
交通ルールや運転マナーが正しく理解できているかの試験です。
学科試験を合格しなければ、技能試験へ進むことはできません。
普通自動車免許を所持している方は、免除となります。
内容はマルバツ形式の2択の問題で、
文章問題が1問1点で90問
イラスト問題が1問2点で5問
合計90点以上で合格になります。
技能試験
適性検査、学科試験をクリアしたら技能試験になります。
この技能試験が一番の難関です。
技能試験の内容は、受験者は一人ずつ、
- クランク
- S字
- 一本橋
- 踏切
などのあるコースを走らされます。
持ち点が100点の状態からスタートする減点方式になります。
乗車するところから厳しくチェックされ、ミスがあると減点されていきます。
最終的に70点以上残っていれば合格です。
スポンサーリンク
試験合格後の手順は?

見事試験に合格した場合は、免許発行までに講習を受けなければなりません。
受ける講習は2種類あり、
- 取得時講習
- 応急救護講習
です。
その後、免許交付という流れになります。
取得時講習
安全に運転するための乗り方や知識を学ぶ講習です。
座学と実技があり、合計で3時間受けなければなりません。
応急救護講習
交通事故で負傷者を救護するための知識を学ぶ講習です。
座学と実技があり、合計で3時間受けなければなりません。
教習所での取得方法についてはこちらをご覧ください。
-

-
原付二種125cc免許の教習所から取得までの流れを紹介!費用や必要なものは?
続きを見る
・合わせて読みたい
-

-
原付二種の年間維持費はいくら?項目ごとに実際に計算してみた!
続きを見る
まとめ
このように、原付二種免許を一発試験で取得するのは、教習所に通うよりも簡単に取れそうなイメージがあるかもしれません。
確かに一回で一発試験を合格できれば楽ですが、逆に10回も20回も一発試験に落ちるのが平均なので、
場合によっては教習所に通うよりも大変かもしれません。